
年初のゲスト講義は1月9日、桃山学院大学(大阪府和泉市)での国際教養学部と社会学部生対象の授業「メディアリテラシー論」(土屋祐子先生)でした。
講話のみ90分、事前に頂いたお題「デジタル絵本ワークショップにみるメディアリテラシーの可能性~ITツール開発と社会実践」に沿って、ITツール開発と社会実践にウェイトを置いた内容としました。「メディアリテラシー論」らしくユニークなのは、今日の講義について<記事>にまとめるという課題が出ていること。学生さんたち自身が、オーディエンスと媒体を想定して書くのだそうです。例えば、開発者向け情報雑誌の記事であったり、子育て世代のためのコミュニティWebの記事、あるいは、不特定多数が読むニュース記事といった具合に。ふさわしい見出しや文体、デザインを考え組み立てて書く。さらに、互いの記事を読みあう予定とのこと。どんな受けとめをされたかシビアに示されるわけで、おそろしくもありますが、それも含めて楽しみです。(写真はキャンパス内のチャペル)
Category: 公教育>大学・大学院

先週~今週、客員教授を務める神戸教育短期大学(学長:三木麻子先生)での講義でした。今年で6年目です。大半の学生さんが長期履修制度(3年制)を利用していて、担当するのはその2年生、保育士や幼稚園教諭をめざす学生さんたちが対象です。
北欧ではデジタル偏重の揺り戻しで紙とペンが見直されていること、オーストラリアや欧州で、子どものメンタルヘルス保護を最優先とし、スマホ・SNS利用の年齢制限や禁止の法規制が始まっていることを紹介。そんな時世だからこそ、最初の出会いが大切で、子どもたちには、ひなたのにおいのする「創る」でICTと出会ってほしい。経済力や文化資本の差といった家庭環境等によらず全ての子どもに等しく届けられるのは公教育であり、相対的評価付けをされない就学前に、子ども自らが取り組みたくなる遊び(=学び)として届けたい。その楽しい学びのデザインができる人になってね、と伝えました。
講話に加えひとり1台環境で実際につくります。録音の段になるとあちこちに輪が生まれ、セリフを複数人での掛け合いにしたり効果音を工夫したりとにぎやかでした。このあと、三木先生が全員分(!)の展開図を印刷してくださるので、ひとり一冊紙の絵本もつくります。
----------------
使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad
ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」
----------------
久しぶりに上京して2つの大学でゲスト講義でした。
7月14日は昭和女子大学 初等教育学科(森秀樹先生)へ。小学校教諭や幼稚園教諭を目指す1年生60人×2クラスが対象です。
ITを活用した楽しい「創る」学び、なかでも言葉の「創る」である物語づくりのデザインができる人になってほしい。そのために、まずは自身でその楽しみを知ってもらおうと、絵本づくりワークショップ的な授業となりました。子どものアクションを引き出す絵本をつくってもらったところ、遊びや生活、冒険といった主題が多いなか、盲導犬について伝えるお話もありました。
ゼミ生さんを交えたランチミーティングでは、外国ルーツの子どもたちをテーマにした卒論に関する質問に答えたり、授業後は森さんがなさっている最近の活動をご紹介いただいたり、充実の一日を過ごしました。
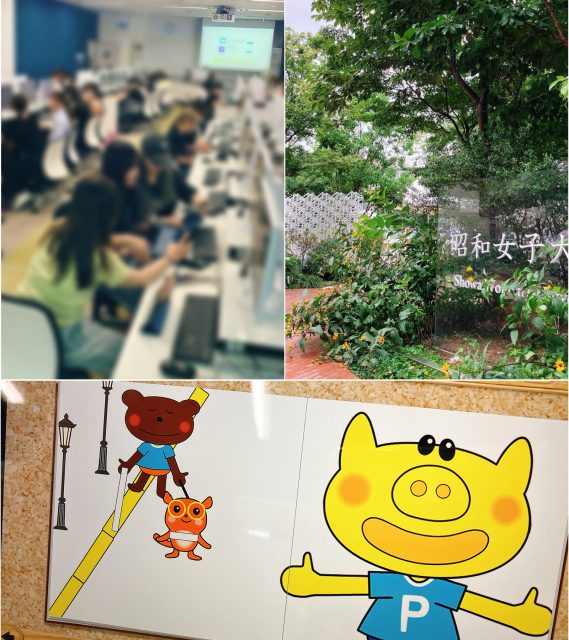
森さんのことは、MITメディアラボの客員研究員であった経歴や、株式会社CSKの社会貢献プロジェクトCAMP立ち上げ期からの初期メンバーとしてScratchやCricketなどテクノロジーを活用した子どものための創造的学びのデザインの先駆者として存じ上げていました。今回お招き頂き、対面でゆっくり話せたのは初めてで、私が特別講義を受けている嬉しさでした。
森さんによるプロジェクト Chobitto (ちょびっと):
https://www.chobitto.jp/
ゲスト講義の様子を 学科Blogにアップしてくださいました:
授業紹介_情報機器の操作「ピッケのつくるえほん」
翌日は青山学院大学 教育人間科学部(杉本卓先生)3年生ゼミへ。2014年からほぼ毎年伺っています。
一般企業へ就職なさる学生さんが大半なので、テクノロジーを何に活かすのかと社会課題を柱にした講話をメインで。外国人など誰かを敵とみなし攻撃する社会になってほしくない小さな試行錯誤を伝えました。体験はごく短時間でしたが、見事な集中力で皆さんほぼ完成。今の自分をつくる成分になっているかも知れない子ども時代のエピソードを物語にしてもらったのですが、例えば、鼓笛隊で指揮者を務めていたけれどほんとは楽器をしたかったと物語ってくれた彼女。このクラスの指揮者(リーダー)です。

『本が死ぬところ暴力が生まれる』『コンピュータを疑え』の翻訳者として1990年代2000年代からお名前を知っていた杉本さんには、Facebookアプリのリリースに際してご助言いただき、ということは2009年頃に出会い、以来お世話になっています。杉本さんは、テクノロジー万歳な人には「いやいや、ちょっと待て」と慎重さを促し、反対に尻込みしている人には「使い方次第ですよ」と寄り添う人で(私の勝手イメージ)、その姿勢に共感を覚えています。静かな言葉に励まされることも多くて、今回も「国連ビル前でデモをするというやり方もある一方、朝倉さんみたいに小さく細く続けるという方法も意味がある。今日の授業も、ひとりかふたりでも心にかかって、今はピンとこなかったとしても、社会に出て、あっ このことだったのかと繋がる日がくるかもしれない」と言っていただけて、都合よく意訳しているかもですが、元気が出ました。
お茶にも詳しくて(『ロマンス・オブ・ティー:緑茶と紅茶の1600年』の翻訳者でもある)いつも美味しい紅茶を淹れて迎えてくださるのも楽しみなのでした。
----------------
使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad
ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」
----------------

7月8日は桃山学院大学(大阪府和泉市)へ出かけ、国際教養学部と社会学部生対象の授業「メディアリテラシー論」(土屋祐子先生)でゲスト講義でした。
事前に頂いたお題「デジタル絵本ワークショップにみるメディアリテラシーの可能性~ITツール開発と社会実践」に沿って、ITツール開発と社会実践にウェイトを置いた内容としました。講話のみ90分を居眠りもせず聴いてくれるので、つい、スライドに含めていなかった詳細まで話しました。日本は出生地主義ではなく血統主義のため、日本で生まれても親の国籍になる。憲法や教育基本法で規定されている「すべての国民」が教育を受ける権利を、解釈や判例によって「日本国籍を有する国民」に限定しているために、外国人の子どもに就学義務はないとされてしまっている。いまSNS等で飛び交う、外国人など誰かを敵と名指し排除し攻撃する言葉は、社会を、自身にとっても生きにくい場所にしてしまう、と。
質疑応答でも活発に質問が出たり、講義後に質問しに来てくれる学生さんもあって嬉しく、猛暑(+ゲリラ豪雨)のなか出かけた甲斐がありました。
「メディアリテラシー論」らしくてユニークなのは、今日のゲスト講義について<記事>にまとめるという課題が出ていること。学生さんたち自身が、オーディエンスと媒体を想定して書くのだそうです。例えば、開発者向け情報雑誌の記事であったり、子育て世代のためのコミュニティWebの記事、あるいは、不特定多数が読むニュース記事といった具合に。ふさわしい見出しや文体、デザインを考え組み立てて書く。さらに、互いの記事を読みあう予定とのこと。どんな受けとめをされたかシビアに示されるわけで、おそろしくもありますが、それも含めて楽しみです。

先週~今週、客員教授を務める神戸教育短期大学(学長:三木麻子先生)での講義でした。今年で6年目です。大半の学生さんが長期履修制度(3年制)を利用していて、担当するのはその2年生、保育士や幼稚園教諭をめざす学生さんたちが対象です。ICTを活用した楽しい「創る」学び、なかでも幼少期に育みたい言葉の「創る」である物語づくりの楽しい学びのデザインができる保育者となってほしいと授業準備をしました。
講話に加えひとり1台環境で実際につくります。録音の段になるとあちこちに輪が生まれ、セリフを複数人での掛け合いにしたりピアノを弾いて歌ったりとにぎやかです。
このあと、三木先生が全員分(!)の展開図を印刷してくださるので、ひとり一冊紙の絵本もつくります。学生さんたち、きっと嬉しいことでしょう。社会に出たとき、物語づくりの楽しみを子どもたちへ届けてくださいね。
そして、今週は台湾の大学院のオンライン授業で話す機会もありました。30分にも満たない時間でしたが、英語のスライドを作成し英語で話すというのは、私にとってかなりのチャレンジでした。学生さんたちも熱心に聞いてくれて、準備~当日、楽しく充実した経験となりました。
----------------
使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad
ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」
----------------
1月6日、嵯峨美術大学の隔年開講授業(内田隆寿先生)でゲスト講義でした(全2回の2回目)。年明けすぐの月曜朝イチ、しかも雨、来週は成人式という2年生もいる中、はたしてどれくらい来てくれるだろうと思いましたが、杞憂でした。今年度はiPad持参者も多く、お正月休みに仕上げて来てあとは録音だけという学生さんもありました。そして、さすが美大生、皆さん、限られた仕様の中で構成や配色を工夫し凝っています。講話は、美大ということもあり、活動デザインなどデザイン視点の話も含めました。2回の講義を通して、物語の楽しみと可能性を知り、それぞれの進む領域で活かしていただけたら嬉しいです。

----------------
使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad
ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」
----------------
12月23日、嵯峨美術大学の隔年開講授業(内田隆寿先生)でゲスト講義でした(全2回)。頂いたお題「社会教育」の切り口で。美大ですし、受講者に教育方面へ進む学生さんは少ないとのことで、自己紹介のところにピッケ以前を含め、大昔につくった3DCGanimeも入れてみました。自身のiPad持参者が大半、しかもiPad Pro+pencil 使いが多いのは、作品制作にタブレットを使う学生さんが年々増えているからだそう。帰り際「家で続きをつくってもいいですか」と質問あり。もちろんOK。年明けの次回が楽しみです。

----------------
使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad
ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」
----------------

先週~来週、客員教授を務める神戸教育短期大学(学長:三木麻子先生)へ出かけています。大半の学生さんが長期履修制度(3年制)を利用していて、担当するのはその2年生、保育士や幼稚園教諭をめざす学生さんたちが対象です。ICTを活用した楽しい「創る」学び、なかでも幼少期に育みたい言葉の「創る」である物語づくりのデザインができる保育者となってほしいと授業準備をしています。
講話に加えひとり1台環境で実際につくります。録音の段になるとあちこちに輪が生まれ、セリフを複数人での掛け合いにしたり効果音を工夫したりとにぎやかです。
子どもたちに、従来の読んでもらう楽しみに加えて、自分でお話をつくり語る楽しみを届けてほしい。ICTを創造の支援に用いて、その楽しい学びのデザインができる人になってほしいと願っています。
----------------
使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad
ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」
----------------
6月11日は桃山学院大学(大阪府和泉市)へ出かけ、国際教養学部と社会学部生対象の授業「メディアリテラシー論」(土屋祐子先生)でゲスト講義でした。
事前に頂いたお題「デジタル絵本ワークショップにみるメディアリテラシーの可能性~ITツール開発と社会実践」に沿って、ITツール開発と社会実践にウェイトを置いた内容としました。
ユニークなのは、今日のゲスト講義について<記事>にまとめるという課題が出ていること。対象と媒体を各自が想定して書くのだそうです。例えば、開発者向け情報雑誌であったり、子育て世代のためのコミュニティWeb、あるいは、不特定多数が読むニュースといった具合に。ふさわしい見出しや文体、デザインを考え組み立てて書く。さらに、互いの記事を読みあう予定とのこと。どんな受けとめをされたかシビアに示されるわけで、おそろしくもありますが、それも含めて楽しみです。
講義後、土屋先生の研究室で3時間超話し込んでしまいました。おかげでメディアリテラシー論界隈について、少しアップデートできました。(研究室の窓には暮れゆく空)


先週~今週は、客員教授を務める神戸教育短期大学(学長:三木麻子先生)へ出かけました。大半の学生さんが長期履修制度(3年制)を利用していて、担当したのはその2年生、保育士や幼稚園教諭をめざす学生さんたちが対象です。ICT を活用した楽しい「創る」学び、なかでも幼少期に育みたい言葉の「創る」である物語づくりのデザインができる保育者となってほしいと授業準備をしました。
講話に加えひとり1台環境で実際につくります。録音の段になるとあちこちに輪が生まれ、セリフを複数人での掛け合いにしたり効果音を工夫したりとにぎやかでした。
子どもたちに、従来の読んでもらう楽しみに加えて、自分でお話をつくり語る楽しみを届けてほしい。ICTを創造の支援に用いて、その楽しい学びのデザインができる人になってほしいと願っています。
----------------
使用アプリ: ピッケのつくるえほん for iPad
ピッケに関するお知らせやレポート: Facebookページ「ピッケ」
----------------









